
[源頼朝や新田義貞ゆかりの新光寺]
| 道幅 | 起伏 | 人通り | 交通量 | 緑 | 風景 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 少 | 普通〜多 | 普通 | 普通 | 街を縫う古道の風景 | 新田義宗 |

|
|
[源頼朝や新田義貞ゆかりの新光寺] |
建久3年(1192)、源頼朝は始めて武家政権を樹立し、鎌倉に幕府を開い た。いわゆる鎌倉幕府である。東国の武士達は早くから頼朝を武門の頭領とし て臣従し政権樹立に大きな役割を果たした。鎌倉街道はこうした東国の御家人 達が一朝ことあれば”いざ鎌倉”と馳せ参じる道筋であった。鎌倉街道の主要 な道筋は上ノ道、中ノ道、下ノ道の3本であったが、その他にも多数の枝道、間 道があった。鎌倉幕府崩壊後も、建武中興、南北朝時代、室町時代、戦国時代 と、時代は移ろっても鎌倉は中世における東国の都として生き続け、鎌倉街道 も幾多の歴史を刻んだ。しかし徳川家康が江戸に入府すると、鎌倉の歴史的使 命は終わり、それに伴い鎌倉街道は歴史の彼方に消え去っていった。
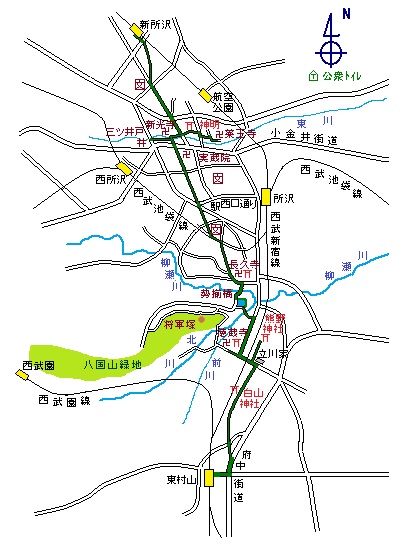
|


|
|
[鎌倉古道碑] |

|
|
[旧久米川宿の入口にあった白山神社] |
白山神社には文政2年(1819)願主北久保忠蔵によって造立された像高6 7cmの牛頭天王(素戔嗚尊)が祀られている。像はもともとここにあったも のではなく、明治の初め頃に井戸の中から発見されたものという。
芳賀善次郎著の『旧鎌倉街道探索の旅 上道編』によれば、かつて白山神社の 裏手には鋭角に切り込んだ谷頭の泉地があり、そこから北へ小川が流れ出て、 この先踏切の北側の道楽ヶ池という細いい池に注いでいたという。今はその川 筋も池も西武線の下になってしまっている。またか神社の南に長い参道があり、 鎌倉時代には参道南に久米川宿南関所があったという。鎌倉道はといと参道南 で線路を越え、線路の西側に沿って北へ伸びていたという。

|
|
[日蓮上人が立ち寄ったかつての立川家] |
文永8年(1271)鎌倉の龍口寺で処刑を免れた日蓮上人が佐渡へ流される ことになった。その折弟子たちは久米川宿まで見送ったという。久米川宿では 日蓮は立川家に丁重迎えられ宿泊したと伝える。
鎌倉江ノ島にある寂光山龍口寺は鎌倉時代は刑場があった所で、立正安国論で 執権北条氏の怒りをかった日蓮聖人は捕えられ、文永8年(1271)ここで 処刑されることになった。日蓮が南へ向かって合掌すると、突然江ノ島方面の 夜空が明るくなり、光を放つ球が飛んできて日蓮の上空で輝いた。これを見た 首切り役人は目が眩み、怖れおののいてその場に倒れてしまった。このことか ら日蓮は処刑を免れ、佐渡へ配流されることになった。世に日蓮の龍ノ口法難 と言われる。日蓮入滅後の延元2年(1337)、直弟子の日法上人がこの奇 跡の地に一堂を建てた。これが龍口寺の始まりという。
⇒⇒⇒ 昔々の多摩話−日蓮上人の龍ノ口法難

|
|
[新田義貞が陣を敷いた熊野神社] |

|
|
[熊野神社境内の富士塚] |
熊野神社は伊弉諾尊、伊弉冉尊、天照大神を祭神とする。元弘3年(1333) 新田義貞の鎌倉攻めの折、新田軍は久米川に陣を敷いた幕府北条軍と激戦の末 打ち破り久米川宿一帯を占領した。義貞は熊野神社境内に布陣し屯営の場所と し、すぐ西にある八国山の将軍塚辺りを監視所として、来る府中分倍河原合戦 に備えた。
古代、水の乏しい茫漠たる武蔵野を通る旅人は難渋を極め、行き倒れになる者 が多かった。天長10年(833)見かねた国府の下級役人6人が自分達の収 入の一部を割いて、多摩郡と入間郡の境に食料や薬品を備えた救護施設を開い た。それが悲田処である。悲田処の所在地は明確ではないが、八国山東麓の久 米川宿界隈にあったという。徳蔵寺東の稲荷神社付近がその跡と推定されてい る。

[元弘の板碑]

[徳蔵寺板碑保存館]

[武蔵悲田処跡]
元弘3年(1333年)後醍醐天皇の討幕の命を受けた上州新田荘の領主新田 義貞は鎌倉北条氏打倒を決意、生品明神でわずか150騎で倒幕ののろしを上 げた。鎌倉街道上ノ道をまっしぐら南下、進軍の過程で足利尊氏が差し向けたニ 男千寿王の率いる200騎の兵が合流、更に東国各地の武士団が次々と参陣し、 ついには総兵力20万の大軍に膨れ上がった。小手指原で激戦のすえ北条軍を 破り、続いてにこの地で久米川合戦が展開され、その3日後には更に南下して 分倍河原で合戦が行われた。分倍河原で勝利した新田軍は、一気に鎌倉へなだ れこみ鎌倉幕府を滅ぼした。八国山の将軍塚はこの久米川の戦の折り、新田義 貞が白旗を立てて倒幕軍の総指揮をとった所と伝えられる。
⇒⇒⇒ 昔々の多摩話−新田義貞の多摩進軍伝説
ところで元弘の板碑は元は八国山の中腹にあった永春庵という小庵の境内にあ ったが、永春庵が江戸時代の後半に徳蔵寺境内に移ったことに伴い、板碑も移 設されたと言う。板碑には次の様な意味のことが記されている。
・飽間斎藤三郎藤原盛貞26歳、5月15日、武州府中にて討死。
・同じく飽間孫七家行23歳、同所にて討死。
・飽間孫三郎宗長35歳、5月18日、相州村岡で討死。
飽間氏が新田方の武将か北条方の武将か定かでないが、日付入りで記された討 死場所は、太平記に記された記述と一致することから、当板碑の歴史的価値が 決定的になったという。

|
|
[広々とした調整池の風景] |

|
|
[新田義貞の伝説を残す勢揃橋] |

|
|
[新田義興開基ともいう野老山実蔵院] |

|
|
[元弘の変の最中に開創された長久寺] |
長久寺は時宗の寺で山号を花向山と号す。鎌倉末期(元弘3年前後)に開山玖 阿弥陀仏(クアミダブツ)によって開創された。本尊は阿弥陀如来である。玖阿弥 陀仏は新田義貞が鎌倉幕府討幕の際、元弘3年(1333)5月に府中分倍河 原で戦死した新田方の武将の供養塔を八国山に建立した人で、阿弥陀如来は当 時から伝来したものという。
実蔵院は真言宗豊山派の寺で、正式には野老山実蔵院正福寺と称す。野老山と は現在の所沢の古い名称野老澤(トコロサワ)に由来する名称である。本尊は大日如 来。武蔵野観音第9番霊場となっている。江戸時代に2度の大火で古文書類を 焼失し、詳しいことはわからないが、戦時中に正平7年(1351)新田義貞 の遺児新田義興が開基と伝える梵鐘が供出されたという。

|
|
[新光寺の枝垂れ桜] |

|
|
[東川畔の弘法の三ツ井戸] |
新光寺は真言宗豊山派の寺で正しくは遊石山観音院新光寺と称す。本尊は行基 作と伝える聖観音菩薩。所沢観音として親しまれている。建久4年(1193) 源頼朝が那須野へ鷹狩に行く途中、ここで昼食をとった折、その時の幕舎の地 を寄進したという。しかしその後戦乱でかすみとられてしまったという。また 元弘3年(1333)新田義貞が鎌倉攻めの折、必勝祈願に訪れ、北条氏を滅 ぼした後には帰途立ち寄り、以前にかすみとられた土地を寄進したと伝えられ る。
弘法の三ツ井戸とは由緒書によれば、昔一人の旅僧(弘法大師)が諸国巡歴の 折、当地の民家に立ち寄り飲み水を求めた。すると機を織っていた婦人が遠方 まで水を汲みに行った。これを見ていた旅僧は村人の難儀を救おうと思い、杖 で三か所の場所を示して印を付け、「ここを掘れば良い清水が得られる」と教 えた。そこで村人が教えられた三か所を掘ると、果たして清水が得られたとい う。三ツ井戸は東川に沿って、ほぼ50mの間隔で掘られ、現存する井戸はそ の東端のものであり、後方には弘法大師をまつる小堂がある。

|
|
[深井醤油のたまり漬直売店] |

|
|
[所沢総鎮守の神明社] |
所沢神明社の創建は詳らかでない。日本武尊が東夷征伐の折、この地に近い小 手指原で休息をとり、天照大神に戦勝を祈願したという。そのことからこの地 の村人がこの地に天照大神をお祀りしたのが始まりという。祭神は天照大神の 他に倉稲魂之命(ウカノミタマノミコト)、大国主命である。

|
|
[新田義宗の伝説を残す薬王寺] |

|
|
[新田義宗終焉の地碑] |
薬王寺は東光山自性院と号す。本尊は身の丈55cmの薬師如来である。境内 には明治30年に義宗の子孫が建てたという『新田義宗終焉の地』碑がある。 これにはこんな伝説がある。新田義貞の戦死後、関東の南北朝動乱を指揮した 三男新田義宗は、幕府足利の攻勢に次第に追い詰められていました。そこで主 な家臣に軍勢を群馬県に引き返らせ、義宗は北国へ落ちて行ったと言いふらせ て、自分はひそかに所沢に隠れ住み再起の時を待った。しかし足利の勢いは止 まらず、ついに南北朝も統一されて戦乱は終わってしまった。義宗は止む無く 剃髪して僧侶となり、隠れ家をお堂に改め、1体の薬師如来を彫刻し、その腹 の中に守本尊を祀り込み、後世の一族再興の祈念と、戦死した一族の菩提を弔 う日々を送った。そして応永20年(1413)この地で亡くなったという。
⇒⇒⇒ 昔々の多摩話−所沢薬王寺の新田義宗伝説