
[国府台城跡から江戸川を望見する]
| 道幅 | 起伏 | 人通り | 交通量 | 緑 | 風景 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | やゝ多い | 普通〜少 | 普通〜少 | 普通〜多い | 郊外の住宅街の風景 | 真間の手児奈 |

|
|
[国府台城跡から江戸川を望見する] |
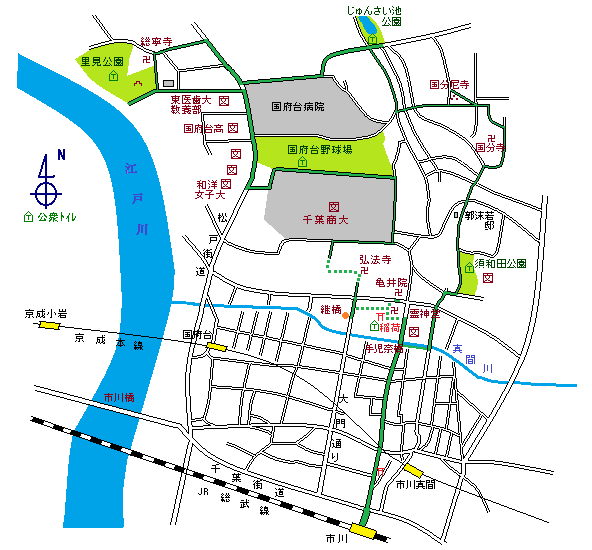
|

治承4年(1180)石橋山で平氏打倒の挙兵をして敗れた源頼朝は、真鶴崎から海 路で安房国猟島(千葉県鋸南町竜島)に逃れた。北条氏、三浦氏、安達氏、千葉氏ら を従え安房、上総、下総へと軍兵を集めつつ進軍した。千葉街道はこの時の道筋と言 われている。江戸川を渡り、隅田川の畔の隅田宿に着いた時は5万の兵力であったと いう。参陣した葛西氏を通じて対岸に対峙する江戸氏を説得して武蔵国へ入り、やが て源氏ゆかりの地鎌倉入りを果たす。

|
|
[真間川に架かる手児奈橋] |

|
|
[手児奈を祀る手児奈霊神堂] |
葛飾の 真間の入江に うちなびく
玉藻刈りけむ 手児名し思ほゆ
山部赤人
手児奈霊神堂は文亀元年(1501)弘法寺の七世日与上人が手児奈を祀るお堂とし て世に広めたという。
手児奈の伝説とは、手児奈があまりの美人のゆえに、幾多の男に求婚され、それがも とで男どもの争いが絶えず、すべての原因は自分にあると自らを責めて真間の入江に 身を投げたという哀れな話しである。その他、真間の井の水を汲んでは継母の孝養に 尽くしたとか、あるいは手児奈は国造の娘で、その美貌を買われ他国の国造の息子に 嫁いだが親同士の不和から海に流され、流れ着いた所が故郷の真間の浦辺であったと か、更には神に仕える巫女であったとか様々な言い伝えがある。
奈良時代の初め、山部赤人は下総国府を訪れ、手児奈の伝説を聞いて次の様な歌を万 葉集に残している。
われも見つ 人にも告げむ 葛飾の
真間の手児名が 奥津城処
山部赤人

|
|
[大門通りにある真間の継橋] |

|
|
[亀井院と門前左に立つ真間井の碑] |
亀井院は日蓮宗の寺で、寛永12年(1635)弘法寺の11世日立上人により弘法 寺管主の隠居寺として建立。湧水を湛える井があることから当初『瓶井院』と称され た。その後弘法寺大旦那の鈴木長常が葬られたことから『鈴木院』と呼ばれるように なった。その息子で幕府作事奉行の鈴木長頼は寺を修造するとともに、弘法寺17世 日貞上人と図り、万葉集に歌われた『真間の井』『真間の手児奈の墓』『真間の継橋』 の所在を後世に伝えるべく、元禄9年(1696)それぞれに銘文を刻んだ碑を立て たという。なお『真間の継橋』とは、昔は真間川が江戸川へ注ぐ河口付近は東に深く 貫入した入江『真間の入江』になっていて、そこに幾つかの洲があったといい、上総 国府から下総国府国府台へ向かう官道にはこの砂州上に幾つもの橋があったことから 継橋の名が生まれた。因みに長頼は宝永2年(1705)日光東照宮修造時の不祥事 で切腹となり鈴木家は没落、寺の名称もは亀井院に改められた。

|
|
[行基が建立した弘法寺の山門] |
由緒書によれば、弘法寺は奈良時代、行基菩薩が真間の手児奈の霊を供養するため建 立した求法寺が始まりで、その後平安時代、弘法大師が七堂を構えて真間山弘法寺と した。しかし鎌倉時代、日蓮の布教を受けて建治元年(1275)日蓮宗に転じ日頂 を初代の貫首としたと伝える。鎌倉末の元亨3年(1323)には千葉胤貞により寺 領の寄進を得ている。室町・戦国時代には真間宿また市川両宿といわれる門前町が発 展し賑わったという。天正19年(1591)には徳川家康より朱印30石を与えら れ、元禄8年(1695)には水戸光圀も来訪したと言われる。明治21年、火災で 諸堂は焼失したが明治23年再建された。
涙石とは正面参道の下から27段目にある石で、沢山ある石の中でこの石だけが常に 濡れているという。宝永2年(1705)作事奉行であった鈴木長頼が日光東照宮の 修築に使う石材を伊豆から船で運ぶ途中、市川の根本付近で船が動かなくなり、積み 荷の石を無断で弘法寺の石段に流用した。その行為が幕府から責められ、ついに責任 をとって石段上で切腹して果てた。以来彼の血と涙がしみ込んで絶えず濡れているの だという。要するに壁に沿って反時計回りに進むのである。

|
|
[下総国府跡に位置する千葉商科大学正門] |

|
|
[下総国府跡とされる国府台陸上競技場] |
式正織部流茶道(シキセイオリベリュウサドウ)とは織田信長、豊臣秀吉に仕えた美濃国の3万 石の大名古田織部生重然(フルタオリベノショウシゲナリ)によって創始された流派である。大坂 夏の陣で豊臣方に内通したとして切腹を命じられ一族は滅亡したが、茶道は古田家の 傍系によって代々継承された。その後門下生に引き継がれ、近年は国府台に住した秋 元瑞阿弥(ズイアミ)が16代を担った。瑞阿弥没後は織部桔梗会が文化財を継承して いる。

|
|
[里見公園の国府台城跡碑] |

|
|
[里見氏の亡霊を供養した供養塔] |

|
|
[伝説の夜泣き石] |
文明10年(1478)扇谷上杉氏の家宰太田道灌はここに城を構え、足利茂氏に追 われ武蔵にいた千葉自胤(ヨリタネ)を助け、千葉孝胤(タカタネ)と戦った。時代は下って 天文、永禄には二度にわたって小田原北条氏と安房里見氏の国府台合戦の舞台となっ た。すなわち天文7年(1538)北条氏綱と足利義明・里見義堯(ヨシタカ)が戦い、 また永禄7年(1564)には北条氏康2万と里見義堯・義弘8千の軍勢が戦ったが 里見は5千もの戦死者をだして敗れ安房へ敗走した。城はその後北条氏によって手を 加えられ戦国の城郭に変貌した。
夜泣き石の伝説とは次のようなものである。永禄7年の国府台合戦で戦死した里見の 武将に里見弘次がいた。弘次の娘は父の霊を弔うためはるばる安房から国府台の戦場 にやってきた。しかしまだ12、3歳の娘は戦場跡の悲惨な情景を見て、傍らにあっ た石にもたれて泣き続けた。そしてついに息絶えてしまった。ところがそれ以後、毎 夜この石から悲しい泣き声が聞こえるようになり、里人はこの石を『夜泣き石』と呼 ぶようになった。ある時一人の武士が通りかかり、哀れな姫の供養をしてからは泣き 声は聞こえなくなったという。
⇒⇒⇒ 昔々の多摩話−国府台の夜泣き石伝説

|
|
[じゅんさい池公園] |

|
|
[旧幕府軍が集結した総寧寺] |
総寧寺は曹洞宗の寺で山号を安国山と号す。永徳3年(1383)近江国観音寺の城 主佐々木氏頼により通幻禅師を開山に近江国左槻庄樫原郷に建立されたが、天正3年 (1575)小田原城主北条氏政により下総国関宿に移した。その後水害を避けるた め、寛文3年(1663)4代将軍徳川家綱により国府台に移転された。明治5年( 1872)学制施行で大学校舎を境内に建設されたが、それが後に陸軍用地となり、 更に戦後の昭和33年里見公園となった。
慶応4年4月11日(1868)の江戸城は無血開城した。翌12日、これに納得で きない旧幕府軍は総寧寺境内に結集、幕府伝習隊を中心にその数2000〜3000 と伝える。その中には陸軍歩兵奉行大鳥圭介や新撰組の生き残り土方歳三等7人がい た。そして大林院(廃寺)で軍議を開き、大鳥圭介を総帥に、また土方歳三を参謀に 選出し北へ転進することを決めた。

|
|
[下総国分尼寺跡] |

|
|
[下総国分寺跡に建つ国分山国分寺の山門] |
天平13年(741)聖武天皇の詔勅により一国一寺の建立が行われた。下総国では 国府のある市川に国分寺が建立されたがその年代は詳らかでない。多分奈良時代であ ろうと言われている。発掘調査の結果によれば法隆寺様式の伽藍配置で、金堂、講堂、 塔の遺構が発見されている。寺名は元は国分山金光明寺と称していたが、明治22年 国分山国分寺と改称された。