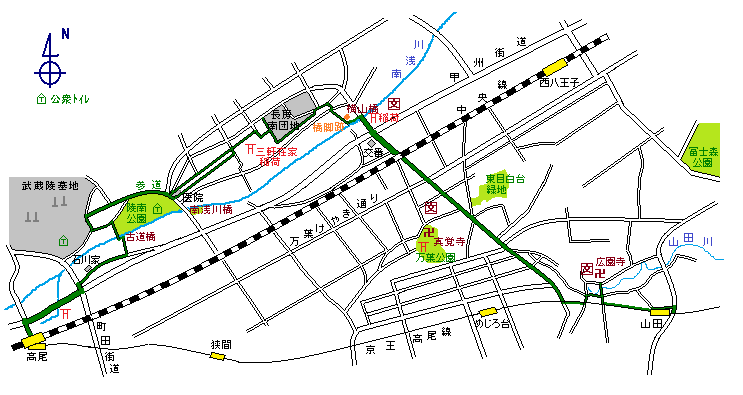旧京王御稜線の廃線跡を行く
距離:約7km
<通過エリア: 八王子>
[廃線シリーズ]
| 道幅 | 起伏 | 人通り | 交通量 | 緑 | 風景 | メモ |
| 広い〜やゝ狭い | 無し | 普通 | 普通〜少ない | 普通 | 町の街路の風景 | 武蔵陵墓地 |

|
|
[住宅街に残された御稜線の橋梁の遺構]
|
多摩にはかつて鉄道が走り今は廃線となった所がいくつかある。その一つに旧
京王御稜線がある。昭和の初頭、大正天皇を祀る多摩御陵(現武蔵陵墓地)へ
参拝客を運ぶ鉄道建設が計画され、昭和6年現北野駅から御陵前駅へ至る路線
が開通した。路線には始発を北野駅に、中間に片倉駅、山田駅、横山駅(後に
武蔵横山駅)、終点に御陵前駅(後に多摩御陵前)が設けられた。しかし参拝
客以外の利用者は少なく、戦火の厳しくなった昭和20年の始め運行を休止、
わずか14年間で幕を閉じた。戦後はしばらく放置されていたが、やがて住宅
開発や高尾山への観光客が期待できることから山田駅から高尾山口まで延伸さ
れ昭和42年現在の京王高尾線が誕生した。これに伴い旧御陵線の山田〜御陵
前間は不要と判断され廃線となった。この辺の事情は山田俊明著「多摩 幻の
鉄道 廃線跡を行く」(のんぶる舎)に詳しく記されている。
今回は廃線となって消滅した御稜線の山田駅から御陵前駅までの廃線跡を辿っ
てみたいと思う。山田駅を出発し、沿線の旧跡を訪ねながら、高尾線との分岐
点からめじろ台東縁の車道に入り、横山駅跡を経て浅川を渡り御陵前駅跡に至
る。その後は武蔵陵墓地を経て帰路に向かい、旧鎌倉道、旧甲州街道を経て高
尾駅に至るものとする。

京王高尾線山田駅を出ると辺りはローカルな雰囲気が漂う。駅前の都道506
号線からすぐ線路の北側に沿って分岐する小道に入る。程なく小道は北西へ折
れて集落へ入る路地になるが、同時にそのまままっすぐ線路沿い築堤下に連な
る幅1m足らずのごく細い抜け道がある。旧御陵線をテーマにしていることか
ら敢えてこの細い抜け道を採ることにする。100mばかり進めばやゝ広い路
地に出る。そのまま進むと緩やかな下り坂となり、それに伴い線路は高架とな
って行く。下りきるとトンネルを通る車道にぶつかる。築堤下の道はここで途
切れるので車道を右折して北側に向かい、浅川の支流山田川に架かる山田橋の
袂で左折して迂回する。なお山田橋の袂から頭を北に向ければ、50mばかり
先に山田の古刹廣園寺の総門を望むことができる。

|
|
[山田の古刹廣園寺の山門]
|

|
|
[御稜線はこの辺りで左方向に分岐していた]
|
広園寺は臨済宗南禅寺派の寺で、正しくは兜率山(トソツザン)伝法院広園寺と号
す。南北朝時代末期の康応元年(1389)、片倉城主長井大膳大夫道広によ
り峻翁令山和尚を開山に創建したという(寺伝では大江備中守師親の開基と言
う)。長井道広は鎌倉幕府政所別当の大江広元の後裔である。広元の次男時広
が頼朝の奥州藤原氏征討に従軍し、その勲功により出羽国長井荘を与えられ長
井氏を名乗った。その子孫が長井道広である。16世紀中頃の戦国時代には塔
頭が49院、末寺が百ヶ寺を数え隆盛を極めたが、天正18年(1590)豊
臣軍による八王子城攻略の折、兵火で焼失した。慶長年間に再興されたが、元
禄10年(1697)再度火災で焼失、文化〜天保年間(1804〜1844)
に再建された。なお広園寺境内は大江氏の居館跡との伝承がある。
山田橋を後にし山田川上流端の標識を左にやり過ごすとすぐ信号のある交差点
に来る。左折すると旧御陵線(現京王高尾線)のガードが見える。多分このガ
ード辺りから御稜線が北へカーブしていたと思われる。ガード下をくぐり線路
の南側に回ると築堤下を線路に沿って上がる坂道がある。坂道を上り続いて長
い階段を上がり切れば線路を跨ぐ跨線橋の袂に出る。跨線橋上に入り東側の山
田駅方面の線路を眺めれば、線路左手北側に三角形状の丘の地形が望見できる。
高尾線から分岐した御稜線はこの丘を築堤として北へカーブしていたものと思
われる。

|
|
[御稜線はガソリンスタンドの左塀沿いを走っていた]
|

|
|
[御稜線が交差する中央線の散田架道橋]
|

|
|
[御稜線が走っためじろ台東縁の通り]
|
跨線橋を渡ると幅の広い車道に変貌する。めじろ台東縁の車道(仮称:めじろ
台東通り)である。道はすぐ大きく左へカーブする。そのカーブ地点辺りに先
の三角形状の築堤の上を分岐してきた御稜線が入ってきたものと思われる。車
道はその後まっすぐに北に伸びる緩やかな下り坂となる。センターラインには
欅並木が連なっている。このセンターライン辺りに御稜線の軌道が走っていた
と言われる。長いだらだら坂を下りきると万葉けやき通りとの交差点に来る。
交差点を過ぎると程なく中央線と交差する。御稜線は高架で中央線を越えてい
たが、今の車道は散田架道橋で中央線下をくぐるようになっている。架道橋を
くぐるとすぐ甲州街道との交差点『並木町』に来る。交差点の南西角地には交
番があるが、その隣の建屋沿いの形状がが微妙に斜めになっている。また甲州
街道の筋向いのガソリンスタンド「ENEOS」と右隣りの建屋との境界が少
し斜めになっていることから、中央線からこの交差点に至る辺りで御稜線はめ
じろ台東通りから離れていったのであろう。そしてここに横山駅があった。

|
|
[南浅川に架かる横山橋]
|

|
|
[駐車場に残るコンクリート橋脚の残骸]
|

|
|
[横山橋の南詰に建つ稲荷神社]
|
交差点で甲州街道を渡り100mも直進すれば南浅川に架かる横山橋の袂に出
る。橋の南詰東側には稲荷神社(稲荷森神社)がある。御稜線は橋の上流50
mばかりの所にあった鉄橋を渡っていたと思われる。実際先のガソリンスタン
ド裏の駐車場には撤去されたコンクリート橋脚跡が残されているのを確認する
ことができる。
並木町の稲荷神社は昔は周辺が鬱蒼とした森であったことから稲荷森神社と呼
ばれていたという。祭神は宇賀御魂命(ウカノミタマノミコト)と木花咲耶姫命。応永5
年(1398)法印弘山によって出羽三山の稲荷大明神を勧請したといわれる。
昭和52年近くの浅間神社が合祀された。
横山橋を渡り、橋の北詰から南浅川に沿って西へ100mばかり進めば集落へ
入る狭い街路がある。街路に入ると右側にたちまち御稜線の巨大なコンクリー
ト橋脚の遺構が2基、民家の庭先に立っている。民家の2階の軒辺りまで達す
る高さだ。御稜線の廃線跡が直接確認できる唯一の遺構である。

|
|
[三軒在家の辻に残る廃線跡らしい空き地]
|

|
|
[丁字路先の民家に沿って丘へ向かった御稜線]
|

|
|
[民家の庭先に残る2つ目の橋脚]
|
狭い街路は程なく別の狭い街路と丁字路でぶつかる。丁字路先の空き地に沿う
民家の並びから御稜線がこの並びに沿って進み、西へカーブしながら前方丘の
上に建つ長房南団地のアパート方面へ向かっていたものと思われる。丁字路を
右折するとすぐ民家の並びに沿う小道が分岐するのでそこに入る。すぐ丘の崖
にぶつかるので階段で丘の上に上がるとそこは長房南保育園の前になる。御稜
線は保育園辺りを通って長房南団地の中を抜けていたと思われるが、廃線跡の
道はないのでここではとりあえず崖の縁に沿って団地の西へじぐざぐと迂回す
ることにする。
団地の西端に回ると車道の一本南側に真っすぐ西へ延びる未舗装の鄙びた小道
がある。小道の右側は民家、左側は車が無造作に駐車する空地と畑、先には南
北に延びる樹林が目に入る。多分この小道沿いが御稜線の廃線跡なのであろう。
鄙びた小道に入り西へ進む。樹林を左にやり過ごすとやがて集落の四ツ辻に来
る。四ツ辻の南東側は細長い空き地になっている。多分廃線跡なのであろう。
この辺りは古くから三軒在家と呼ばれる所で、南側の集落の中にはささやかな
三軒在家稲荷神社がある。祭神は稲荷神と宇迦之御魂神。この近くに鎌倉街道
山ノ道の道筋が走っていることから、三軒在家は八王子城の北条氏照の家臣だ
ったかもしれません。

|
|
[集落の中にひっそり佇む三軒在家稲荷神社]
|

|
|
[御稜線の終点御陵前駅があった辺り]
|

|
|
[東京オリンピックの自転車競技場だった綾南公園]
|
四ツ辻から住宅街の街路をそのまま西へ真っすぐ進む。御稜線はこの街路と一
本南の街路との間の巾20mばかり宅地を走っていたものと思われる。街路は
程なく武蔵陵墓地の広い参道に合流する。合流点には近藤内科医院があり、こ
の辺りが御稜線の終点御陵前駅だった。参道の筋向いは綾南公園になっている。
1964年の東京オリンピックの折に自転車競技場として使われ、その後公園
になったものだ。
廃線跡の追跡は終わったが、これより御稜線が建設目的としていた武蔵陵墓地
へ向かうことにする。綾南公園を左に見ながら鬱蒼とした欅並木の参道を進む。
欅並木の参道は大正15年(1926)大正天皇崩御により、当時の東京府南
多摩郡の横山村、浅川村及び元八王子村地域に御陵所を造営することとなり、
これに伴い中央線の八王子駅と浅川駅(現高尾駅)間に仮駅(後に東浅川宮廷
駅)が設けられ、南浅川には南浅川橋が架けられ、御陵に至る約800mの参
道が新設された。参道には約160本の欅が植樹された。今は20mを超える
巨木になっている。

|
|
[昭和天皇の武蔵野稜]
|

|
|
[武蔵陵墓地の正面入口から総門を望む]
|

|
|
[鬱蒼とした欅並木に包まれた参道]
|
程なく武蔵陵墓地の正門入口の前に来る。墓地には現在大正天皇の多摩陵、貞
明皇后の多摩東陵、昭和天皇の武蔵野陵、香淳皇后の武蔵野東陵がある。参拝
時間は午前9時から午後4時まで、入場は誰でも自由である。ただ陵墓地は広
大でいずれの陵墓も正面入口から400m以上も奥にあるので注意が必要だ。
武蔵陵墓地の内部は、正門を入ると広い空間の先に総門がある。総門を抜ける
と深い樹林で囲まれた玉砂利道の参道が続く。程なく参道は二手に分かれる。
真っすぐ進めば大正天皇と皇后の多摩陵と多摩東陵があり、北への新参道を採
れば昭和天皇と皇后の武蔵野陵と武蔵野東陵がある。いずれ陵墓も重厚な石の
鳥居を構えた先に上円下方の陵形で造営されている。
これより帰路に入り終着駅の中央線高尾駅へ向かう。武蔵陵墓地正門前から石
畳の狭い街路に入る。この街路は鎌倉街道山ノ道の道筋と言われる。源頼朝を
部門の頭領と仰ぐ武蔵武士達が『いざ鎌倉』と馳せ参じた道筋である。程なく
丁字路帯の右角地に小さな堂宇がある。中には3基の石仏石塔が立っている。
右端の大きな石塔は安永年間造立の庚申塔である。丁字路帯を右折して南に向
かうと下方に南浅川を望む崖上に出る。崖を下ると南浅川に架かる古道橋の袂
に出る。もちろん古道橋とはここが鎌倉道の道筋であることを意味している。
橋の欄干には騎馬姿の鎌倉武士のレリーフが飾られている。

|
|
[鎌倉道沿いに立つ石仏石塔]
|

|
|
[南浅川に架かる古道橋]
|

|
|
[石川日記で知られる千人同心の石川家屋敷]
|
中世の頃、東国の武士達が彼らの居館と鎌倉との往還に踏み固めた道筋が鎌倉
街道となった。鎌倉街道には幾筋かあり、主なものに上ノ道、中ノ道、下ノ道、
山ノ道等の道筋があった。今回の道筋はそのうちの山ノ道と呼ばれる道筋に相
当する。遠く信州から碓井峠を越えて群馬高崎に入り、秩父を経て多摩に入る
と小沢峠、松ノ木峠、榎峠を越えて青梅の軍畑へ。軍畑から多摩川を渡河し、
平井を経て秋川を渡り、網代から秋川丘陵を越えて八王子に入り、高尾から町
田を経て鎌倉へ通じていた。平安末から鎌倉初頭にかけて、源平合戦で活躍し
た桓武平氏の末で、武蔵武士の鑑と称えられた畠山庄司重忠は、居館のあった
秩父から馬に騎乗し、郎党をひき連れてこの道筋を粛々と鎌倉へ向ったのであ
ろう。
古道橋を渡り住宅街を縫う石畳の鎌倉道の小道を進むと幅の広い通りと丁字路
でぶつかる。この通りは旧甲州街道である。現甲州街道はここより住宅を挟ん
で南側に走っている。右折して旧甲州街道を進む。ほどなく沿道右側に古びた
黒い廻り塀の旧家がある。石川日記で知られる千人同心石川家の屋敷である。
石川家は甲州武田氏の家臣の家系で、江戸時代には千人同心として徳川家に仕
えた。享保5年(1720)石川善兵衛の時、天気や農作業などの日常の生活
記録のほか、千人同心の公務である日光勤番などを書き記した日記、いわゆる
石川日記を書き始めた。日記は200年以上書き継がれており、歴史を知る貴
重な資料として八王子市指定有形文化財となっている。
交差点『町田街道入口』で銀杏並木の甲州街道に出る。終着高尾駅には甲州街
道経由でもよし、あるいは交差点南西角地にある熊野神社の傍らの狭い路地を
経由してもよし、いずれにしても高尾駅はもうすぐだ。
多摩のジョギング道 ( http://tamamichi.life.coocan.jp/ )